発達障害と不登校の関係|特性に応じた支援でできること
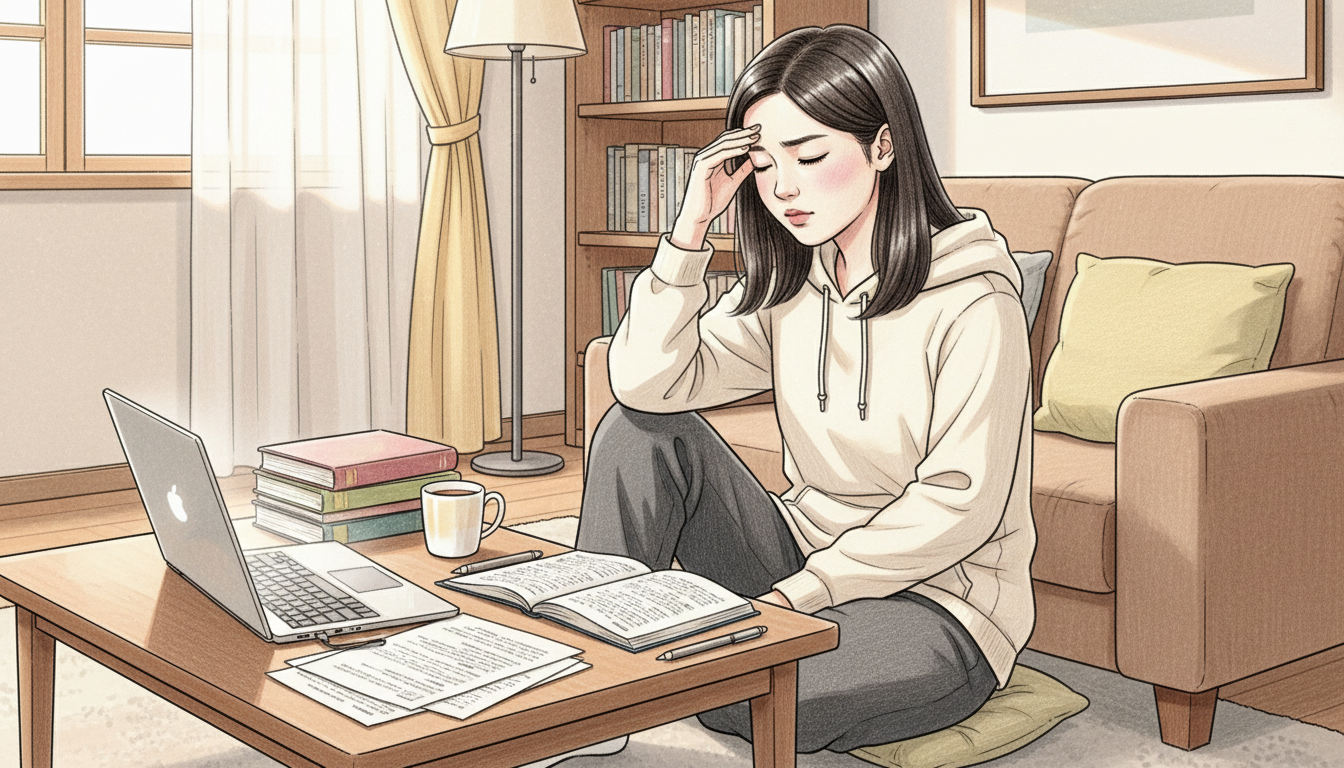
「学校に行きたくない」「行けない」。お子さんがそう感じているとき、保護者としてはとても心配になりますよね。不登校の背景には様々な要因がありますが、中には、得意なことと苦手なことの差が大きく本人は頑張っているのに上手くいかないケース、発達障害(ASDやADHDなど)の特性が色こく集団生活に苦戦しているケース、感覚の過敏さが生活を邪魔して学習や集団生活が苦しいケース、など個性によって他のクラスメイトよりも学校生活でエネルギーを必要とするケースは一定数います。
現在、教育界にはUDL(ユニバーサルデザインフォーラーニング)という言葉が広がりを見せています。障害の有無ではなく、全ての児童生徒にとって学びやすい環境を提供していく中で、あるいは、特徴の有無関係なく全ての子どもの健全な発達を考える上で、発達障害の特性理解は、全ての子どもに対して理解に基づいた支援を行うことに繋がります。ある専門家は、発達障害の特徴を「ジュースの原液」で表現されていたことがあります。どれくらいの濃さなのか濃度は様々だが、どの人にも、関連した特徴はあって明確な線引きをするよりも、濃さで理解する方が良い。とのこと。
そうした意味で、本記事に目を通していただくと、今まで気づかなかったお子さんの特徴や得意・苦手をつかむヒントが見つかりお子さんが少しでも生きやすくなる道を見つけられるかもしれません。以下、発達障害のある子どもの不登校について、その背景や支援方法を分かりやすくお伝えします。
発達障害と不登校の関係性
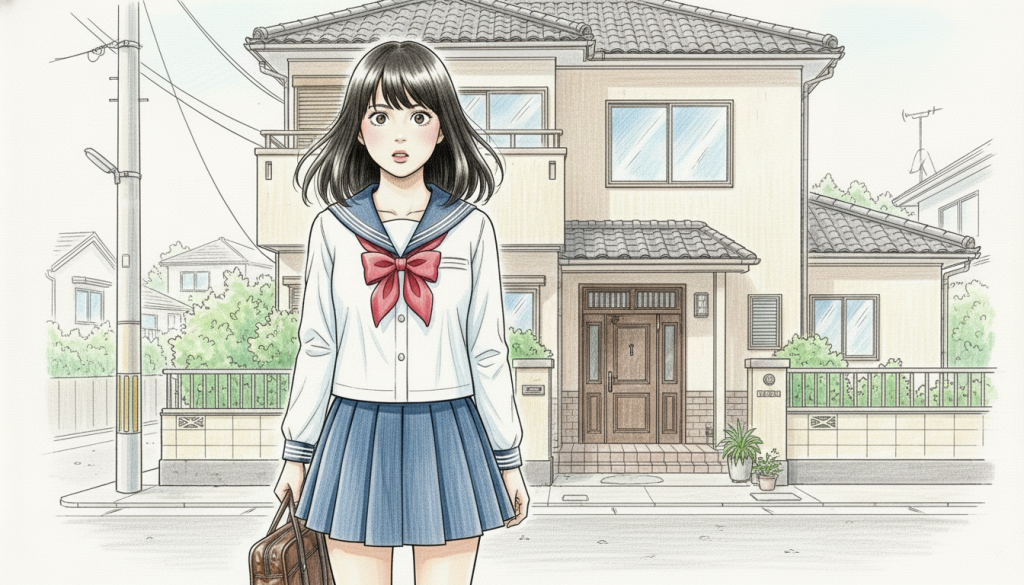
文部科学省の定義によると、不登校とは「心理的、情緒的、身体的、または社会的要因・背景により、年間30日以上登校しない、または登校したくてもできない状況」を指します。発達障害のあるお子さんにとって、学校生活はその特性ゆえに大きなストレスを伴うことが多く、不登校の一因となることがあります。

発達障害の特性が不登校に与える影響
ASD(自閉スペクトラム症)
ASDの子どもは、他者の気持ちを想像することが苦手だったり、言葉を文字通りに受け取る傾向があります。そのため、友人関係や教師とのやりとりで誤解や摩擦が生じやすく、学校生活が負担になりがちです。たとえば、自身が感じたことが、周囲から「ずれている」「間違っている」と指摘を受ける機会ばかりになると、自信の低下や周囲への反発につながる恐れがあります。
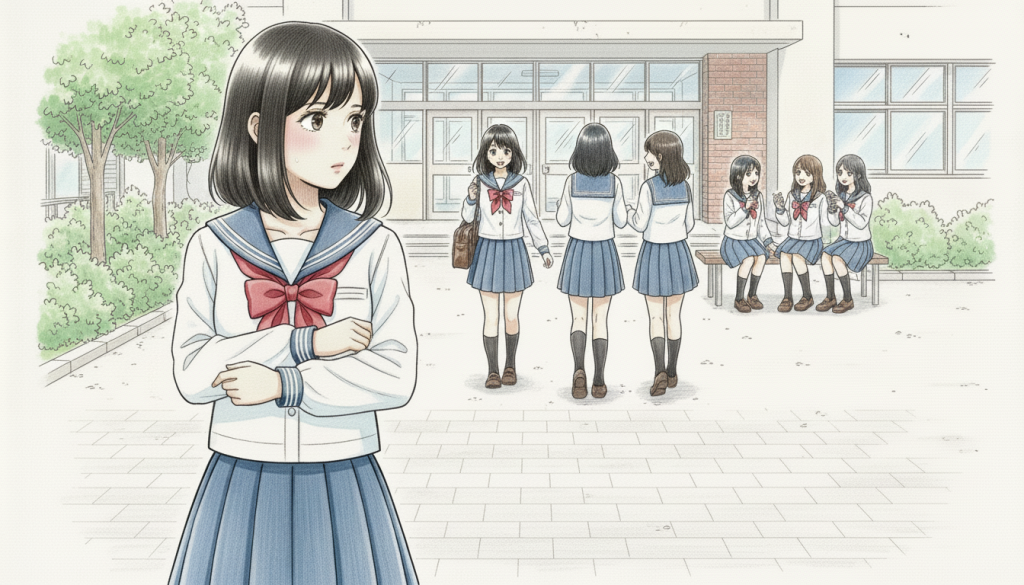
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDの子どもは、注意散漫や衝動的な行動、多動性などの特性から、授業についていけない、忘れ物が多い、叱られることが多いなどの困難を抱えることがあります。決して悪気やわざとではないのに周囲から叱責を受けたり、失敗して恥ずかしい思いをする体験が積み重なると、「学校にいくと嫌な思いをする」ということを学び、学校に行きたくなくなることがあります。
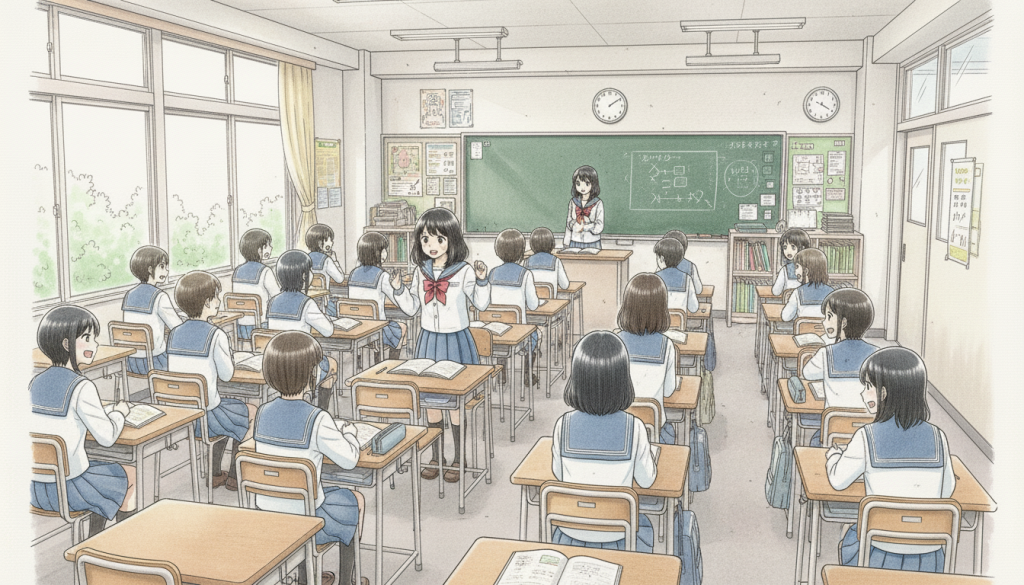
前述の例えでお伝えした「ジュースの原液」です。発達障害の特性は、まるで濃いジュースの原液のようなもの。個性そのものは決して悪いものではなく長所にも十分なり得ますが、周囲の環境や支援(=水や氷の量や質)が適切でないと、その特性が強く出すぎてしまい、本人も周囲も困難を感じることがあります。
逆に、特性に応じた合理的な配慮や環境調整が行われれば、子どもたちは自分の力を発揮しやすくなります。

自己理解と「自分のトリセツ」を持つこと
発達障害のある子どもたちが生きやすくなるためには、自分自身の特性を理解することが大切です。これを「自己理解」と言います。自分の特性を知り、それをどう扱えばいいのかを学ぶことで、子どもたちは少しずつ「自分の取扱説明書(トリセツ)」を作っていくことができます。
思春期の後半に入ると、「自分のトリセツ」という表現は、今後の進路を考える上で比較的ストンと子どもたちに入っていきやすい表現になるかもしれません。
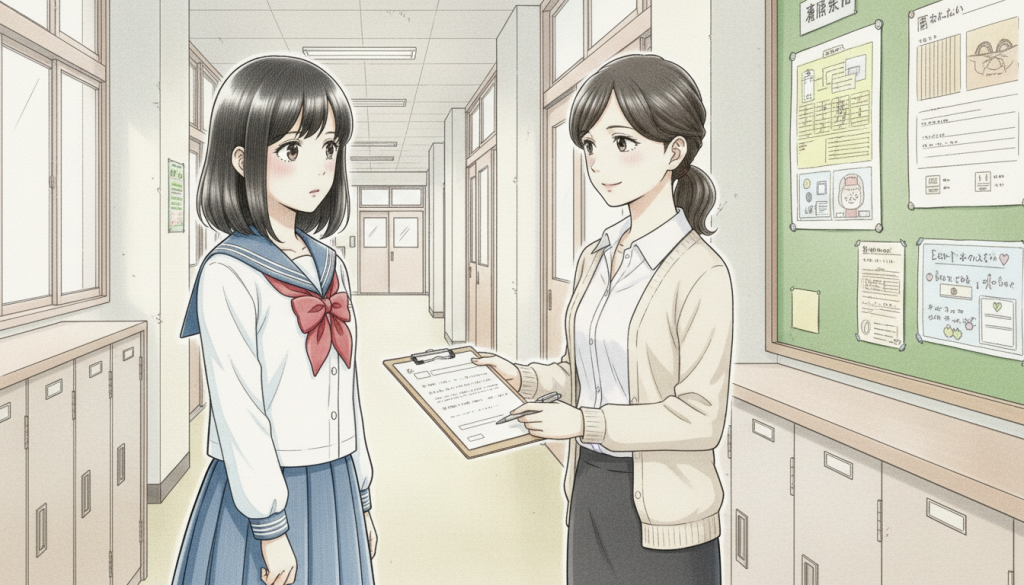
発達検査とタイミングの重要性
自己理解を深めるためには、発達検査が役立つことがあります。ただし、検査を行うタイミングには注意が必要です。特に思春期の真っ只中(前半)では「自分が他者と違う」という事実を受け入れにくい場合があります。一方で、まだ他者と自分を比較しない児童期や、「これからのために自分のことを知りたい」と思えるタイミングでの検査は、子どもにとってポジティブな体験にもなりえます。
支援のポイント:合理的配慮と専門機関連携
発達障害や特性が引き金となる不登校の背景には、学校や家庭生活での失敗体験も絡み合っています。成功体験を積み重ね、自体が深刻化せずに前に進んでいくために、発達検査を受けるチャンスがあったとしても受けて終わりではなく、専門家から受けたフィードバックを手がかりに、実生活の中でどのように運用していくと良いか、試してみて様子を観察し、修正しながら羅針盤のように活用する、という意識で進めていくことが重要なポイントになります。
1. 特性に応じた合理的配慮
周囲が特性だと気づき、本人の悪気や故意ではない、という共通理解が広がれば、本人の踏ん張りに歩み寄った配慮、環境整備に自然と気持ちが向いていきます。たとえば、学校では、授業中に席を自由に移動できる環境を整える(ADHDの多動性への対応)、曖昧な指示ではなく、具体的で分かりやすい指示を出す(ASDの特性への対応)ように心がけるといった具合に、しんどさを少し軽減できるように協力するムードを作っていくことが可能になります。「個別の学習計画」「支援計画」を立てる、ということのメリットは、まさに上記のような共通理解・手立てを忘れないように視覚的に理解できるロードマップになる、ということになります。
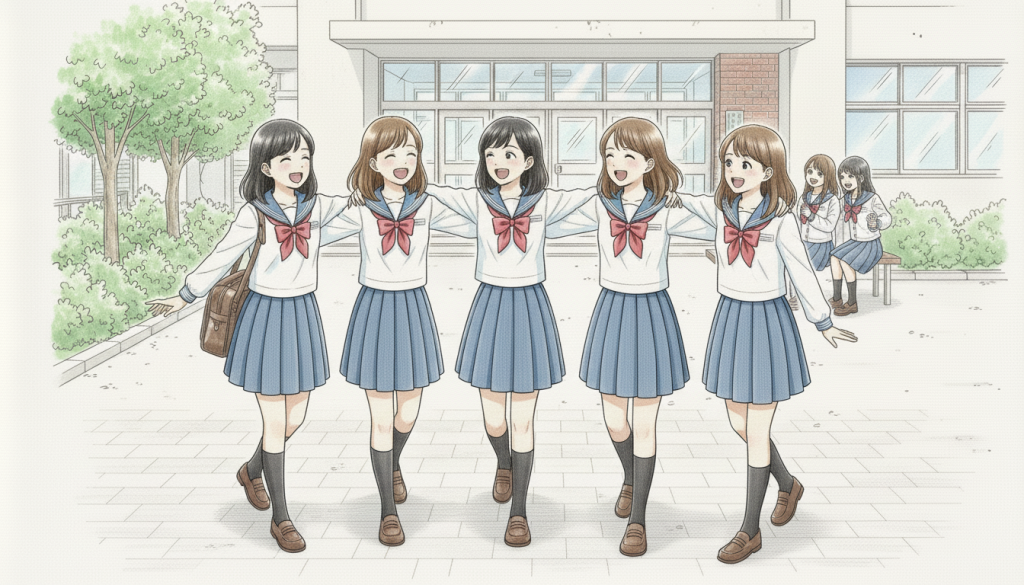
2. 専門機関との連携
スクールカウンセラーや発達支援センター、医療機関などの専門家と連携し、子どもの特性に応じた支援を行いましょう。子育ての経験と勘だけに頼らず、何より保護者の方がお一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用し立体的に子供を理解することが大切です。

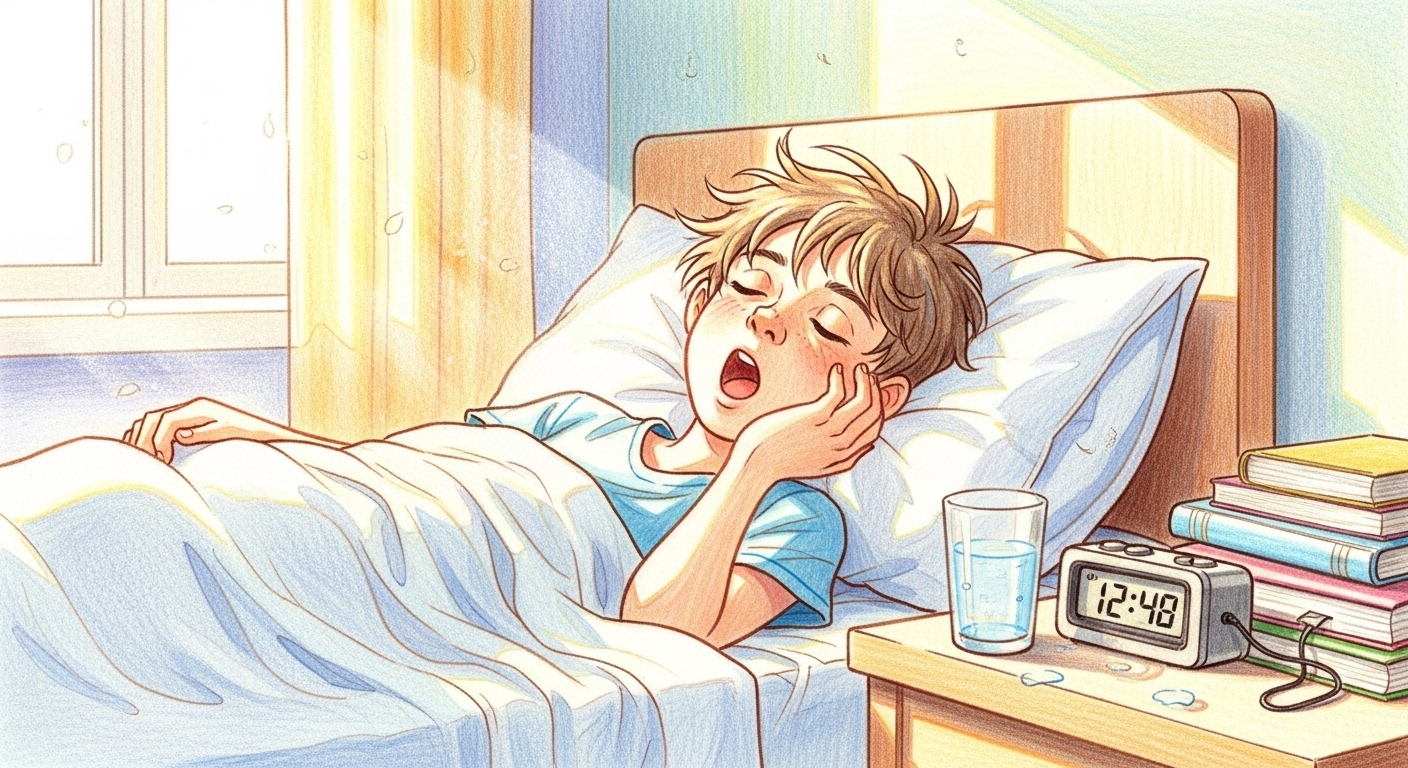
まとめ:誰もが「濃い薄い」を持っている
発達障害のある子どもたちは、特性という「ジュースの原液」を持っています。それは決して悪いものではなく、周囲の環境や支援次第で、その子らしい輝きを放つ「才能」にもなります。
「不登校」という状態は、子どもが抱える何らか困難のサインと捉えるのが良いでしょう。状態を責めるのではなく、その背景やこれまで抱えてきた気持ち、その子なりに踏ん張ってきたことを理解し、寄り添いながら支援することで、子どもたちは安心して自分のペースで成長していけるでしょう。
最後に、不登校や発達障害についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、専門家に相談してください。きっとお子さんに合った道が見つかるはずです。

